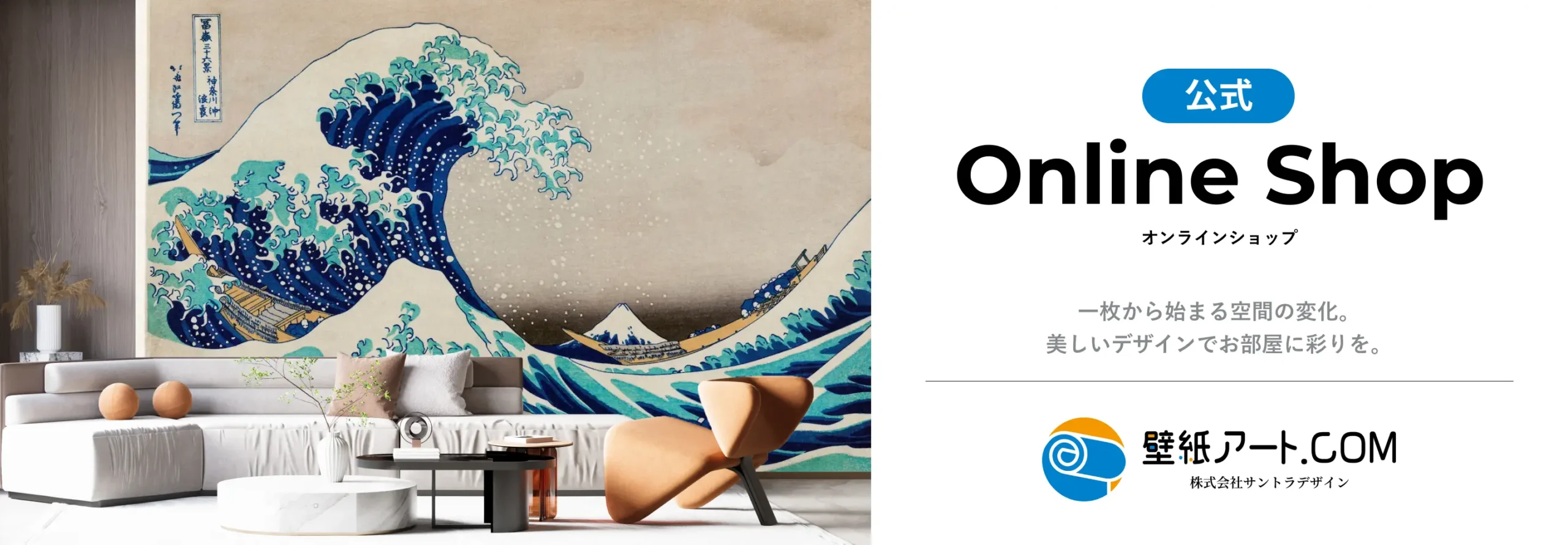先日、ニューヨークで行われたオークションで、誰もが一度は目にしたことがあるだろう、富士山を背景に荒波が飛沫を上げる「神奈川沖浪裏」を含む『富嶽三十六景』全作品が、約5億4000万円という、版画作品としては破格の高値で落札されたことが話題を呼んだ、もはや世界に名だたる人気「芸術家」のひとりとなっている江戸時代の絵師・葛飾北斎。 しかしながら、その出自についてはもちろん、実に90回以上も引っ越しを繰り返し、「勝川春朗」にはじまり「葛飾北斎」を経て、やがて「画狂老人卍」に至るまで、30以上の画号を用いながら、満88歳で没するまでのあいだに、膨大な数の作品を残した彼の生涯は、当時の絵師たちの多くがそうであるように、依然として多くの謎に包まれている。 リストラ間際の崖っぷちサラリーマンが、江戸時代にタイムスリップして、来年の大河ドラマの主役となることも決定している江戸時代の凄腕出版人「蔦屋重三郎」のもとでビジネスを学ぶというエンタメ歴史小説『蔦重の教え』(双葉文庫)の著者であり、浮世絵・江戸料理文化研究家でもある車浮代が著した本作『気散じ北斎』(実業之日本社)は、そんな北斎の「気散じ」な生涯を駆け足で把握するには、うってつけの一冊となっている。「鉄蔵〈こと北斎・十二歳〉 明和八年(一七七一年)」、「勝川春朗〈こと北斎・二十三歳〉 天明二年(一七八二年)」、「北斎〈四十二歳〉 享和元年(一八〇一年)」など、時系列に沿って並べられた短い断章で、なおかつ小説の形式で描き出される北斎の生涯。 しかしながら、本作の面白いところは、それだけではなかった。そこにもうひとりの人物の生涯が、重ねられているのだ。その人物の名は「お栄」――北斎の娘であり弟子であり、「葛飾応為」の画号で後世に知られる女性絵師だ。 杉浦日向子の漫画『百日紅(さるすべり)』(実業之日本社)と、それを原恵一監督がアニメ映画化した『百日紅~Miss HOKUSAI』(2015年)、あるいは朝井まかての『眩(くらら)』(新潮社)と、それをNHKがドラマ化した『眩~北斎の娘~』(2017年)など、当時は珍しかった女性絵師として、近年は北斎以上にその存在が注目を集めている葛飾応為。一度は嫁に出るも、いつしか北斎の家に出戻って、北斎のアシスタント的なことをしながら(ときには、北斎の代わりに絵を描きながら)、「葛飾応為」の名前で「吉原格子先之図」など、国際的にも評価の高い肉筆画を残している「お栄」。北斎とお栄――父と娘でありながら師匠と弟子でもある、この奇妙な親子の生涯には、蔦屋重三郎はもちろん、東洲斎写楽、喜多川歌麿など、同時代の絵師たち、さらには曲亭馬琴といった戯作者たちが、深く関わっているのだった。 「蔦屋重三郎 寛政五年(一七九三年)〈春朗こと北斎・三十四歳〉」、「東洲斎写楽 寛政六年(一七九四年)〈春朗こと北斎・三十五歳〉」など、これまた時系列に沿って並べられた短い断章で、綺羅星のように次々と、現れては消えてゆく同時代の文化人たち。当時としては、かなり長寿をまっとうした北斎は、そしてそんな北斎の傍らで絵を描き続けたお栄は、彼らとの交流を通して、一体何を感じていたのだろうか。 けれども、本作の何よりの「読みどころ」は、そのクライマックスになるのだろう。本書の出版に合わせて、著者自らが「構想8年、取材と交渉を重ね、各界の専門家の方々にご意見を賜りながら、これまでの定説を覆す、大胆な仮説を立てて書き下ろしました。私が追い求めていた北斎のお栄の関係を、ようやく世に出すことができます」とコメントしているように、本作の最後には読む者をみな驚かせる、実に大胆な「仕掛け」が用意されているのだった。多くの謎に満ちた生涯であるがゆえに「そうであったかもしれない」可能性に満ちた本作。それもまた、歴史を楽しむひとつの醍醐味なのだろう。
目次