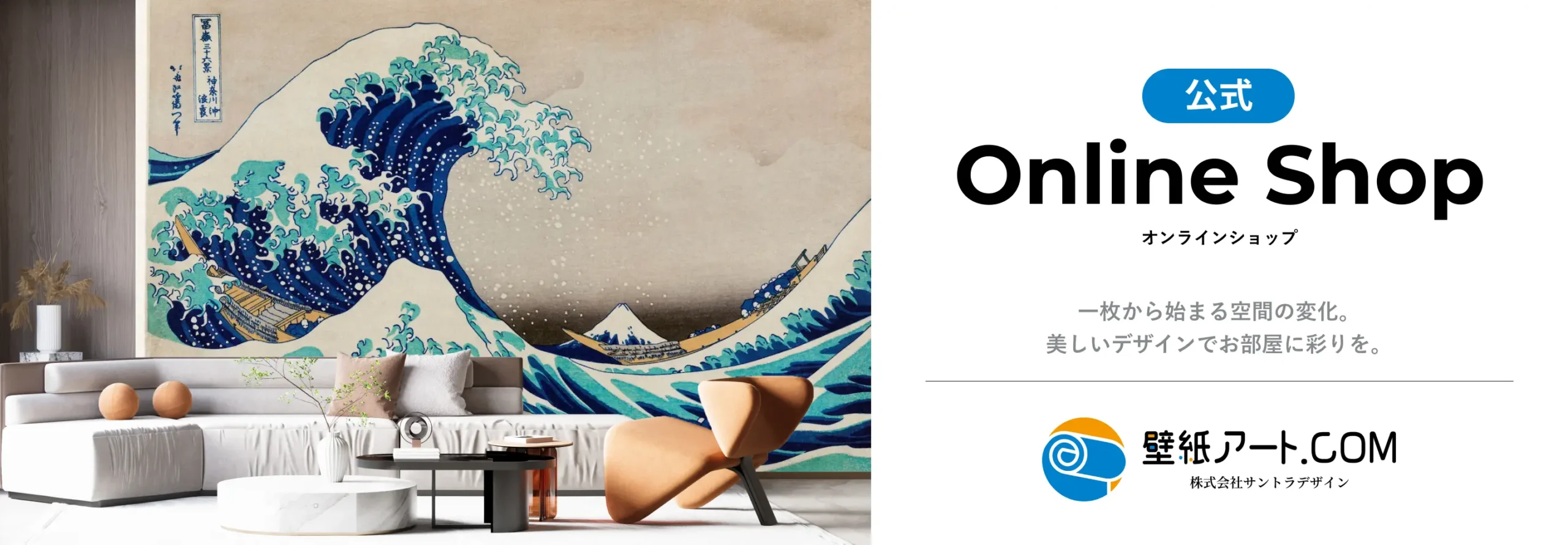来たるべき「クルディスタン」絵画 まず、マドハット・カケイという稀有な画家が、なぜ新潟の砂丘館で個展を開くに至ったかについて伝えておく必要があるだろう。といっても話は相当に込み入っている。だいぶ荒っぽくなるが、概略に留めるほか選択肢はない。それでも冒頭でその話をするのは、その経緯が彼の現在の作品に大きな影を落としていると感じるからだ。まず、カケイは最初、日本で「モハメッド・M・アリ」という名で紹介された。聞いた人は皆アラブ系の画家なのか、と思うに違いない。しかしそれがそうではないのだ。 カケイを日本で広く紹介したのは、『芸術新潮』に長く連載された名物エッセイ「気まぐれ美術館」の書き手で知られる洲之内徹。かつて銀座で「現代画廊」という画廊を運営していて、ずば抜けた絵の目利きで知られた。「批評の神様」と呼ばれた小林秀雄は、美術批評のいわゆる「御三家」(針生一郎、中原佑介、東野芳明)を押しやって、洲之内を当代一の批評家と高く買っていた。もっとも、本人にそのつもりはなかっただろう。むしろ批評家を嫌っていたから。 その洲之内の画廊にカケイが顔を出したのは初めて来日した1986年、カケイが美術を学んだマドリードの美術学校で一緒だった日本人の知人から教えられてのことだった。これを機に洲之内は千葉に共同でアトリエを構えたカケイを訪ね、そこで彼の作品に惹かれる。今回の展覧会ではその頃の絵もたくさん展示されている。千葉のアトリエは元診療所であったという和洋折衷の建物を改造したもので、カケイは取り外した襖などに、なんのためらいもなく自由に絵を描いた。主に女性をもとにしたもので、マドリードで学ぶようになる前、カケイは自分が生まれた国であるイラクのバグダッドで、かつて中国で版画を習ったという美術教師に付いていたという。洲之内は、カケイの絵を初めて見たとき、なぜだか「身近さ」「懐かしさ」を感じたという。そしてカケイの先生は、それまで中国で仏教の経典などに付された絵を複製する手段でしかなかった版画に、初めて創作という概念をもたらした魯迅(*1)の影響下にあったのではないかと推測する。 じつは魯迅がこのような版画の革新に至ったのには、日本の浮世絵(版画)への造詣が深かったという経緯がある。魯迅は北斎、広重、歌麿などを好んだが、そもそも版画は中国に源流があり、それが日本に伝わって浮世絵として独自の分野を形成することになった。それが、魯迅の手で再度、中国にもたらされてさらなる革新を遂げ、国が乱れた結果、貧しさに喘ぐ民衆の表現手段として広まった。かつて社会主義運動に身を染めた洲之内の目がそれを「身近」「懐かしい」と感じたのもゆえなきことではない。 いま「国が乱れ」と書いたけれども、先にカケイが生まれた国を「母国」と書かなかったのには理由がある。カケイは民族でいうとアラブ系ではなくクルド系に属する(ゆえに名前を現在のものに変えている)。クルド人は国こそ持たないものの、古くからクルディスタンと呼ばれ、イラク北部、イラン西部、トルコ東部、さらにはシリアからアルメニアにわたり広く暮らしている。言語も違う(クルド語)し、文化も宗教(カケイの名はゾロマスター教に由来する)も異なる。だが、それゆえに国籍を置く国では様々な矛盾や軋轢の的となる。 事実、1980年にイラン・イラク戦争が勃発すると、クルド人たちは最前線に駆り出され、同じ民族で殺し合う場面に直面した。これを耐えがたく感じたカケイは戦線を離脱。敵国イランの山岳に逃れ、東欧ポーランドに渡り、さらにスウェーデンへと亡命した(いまでもストックホルムを拠点としている)。 今回は出展されていないが、初期作品にはそのような苦悩や矛盾を版画にしたものが少なくない。その手法が中国の魯迅の革新によって生み出され、悩める民衆の内面を吐露するための創作版画を通じてカケイの作品へと転生し、そのカケイが浮世絵の出自である日本にアトリエを構えるようになって、その伝手をたどり洲之内と巡り合ったことには、偶然では片付けられない奇縁を感じる。 浮世絵ということでいえば、今回の会場となった砂丘館はただの日本家屋ではない。もとは大正3(1914)年に全国で10番目に開設された日本銀行新潟支店の支店長役が代々住んだ邸宅なのだ。敷地はおよそ523坪、延べ床面積だけでもおよそ152坪に及ぶ。実際、足を踏み入れてみればわかるが、2階も含めるとひとりでは迷子になりそうなほど設計に手が込んでいる。窓からは風情ある庭も眺められる。 こんなことを言うと、日本間の持ち味を生かした展示室の数々は、さぞかしカケイの作品に合うだろうと思うかもしれない。だが、ことはそう単純ではない。というのも、カケイはあるときから作風をガラリと変えて、現在では抽象画が主になっているからだ。だが、そこはカケイのこと。抽象画といっても特別な描き方なのだ。一見してはモノクロームの絵画に見えるかもしれない。けれども、その印象はすぐに揺らぎ始め、近づいて見たとき、これらの絵がじつに複雑な色調を持っていることに気づく。驚くことに、支持体から盛り上がるほど何層にもわたって絵具が盛られ、正面から見えていた色面は、その背後にある数えることができない色層の最上部にあって、背後の色の積み重ねを反映した最後の画面であることがわかるのだ。それはとくに絵のヘリの部分において顕著で、それぞれの色面の背後にどんな色が塗られていたかが(ものにもよるけれども)はっきりと垣間見られるようになっている。 わたしにはこれが、カケイの生きてきた軌跡が何度でもいまある生きた色によって塗り重ねられ、どんな「単色(モノクローム)」でも再現することができない多色性を生み出しているように感じられた。そもそも、現在の世界情勢が深刻に示している通り、国民国家という「単色」の国家装置は、ほかならぬ戦争の火種となる。それは民族を分断し、殺し合いを強いる。カケイの絵は、それとは根本から異なる世界観を招来しているようにわたしには思われた。つまり、近代の国家を輪郭づける国民国家というモノクロームの世界観からは決して発出しない、いつか招来されるべき「クルディスタン」という世界観がそうであるように。そしてこのクルディスタンに由来する国境に支配されない、あえて言えば陸の群島的な色面の多層性を、カケイの絵は確かに備えている。それは決してわかりやすく政治的な作品ではないけれども、たんに政治的な作品と言ったときにわたしたちが思い描くのとは根本的に違う意味で、カケイの絵はわたしたちがやがて到達すべき新しい世界の在り方を絵の力によって示している。 このカケイの絵が持つ群島的な世界観の可能性に強く関心を示したのが、2022年末に亡くなった建築家の磯崎新であった。磯崎がかつて開いた展覧会には「海市──もうひとつのユートピア」(1977)、「都市ソラリス」(2013~14、いずれもICC)というのがあったから、群島というなら、それに倣ってカケイの絵画が持つイマジナリーな色層の持つ在り方をあえてそう呼んでもよい。とにかく磯崎はこのカケイに頼まれ、新たな美術館の設計のための初期調査として、遠くイラク北部の都市キルクーク郊外(キルクークはカケイの生まれた地でもある)を訪ねている。 そんな磯崎にカケイを紹介したのは、美術評論家の針生一郎だった(針生もカケイの絵の初期の紹介者のひとりだ)。磯崎の回想では、カケイと初めて会ったのはイラク戦争でアメリカ軍がイラク全土を制圧し、戦闘で拘束した捕虜を搬送・収容したキューバのグアンタナモ収容所での拷問にも等しい捕虜の扱いが非人道的だとして、世界中で報道されていた頃というから、おそらく2004年のことではないだろうか。事実、磯崎が訪ねたイラク北部は油田資源の拠点ということもあり、米軍のパトロール隊が定期的に巡回しているような場所だった。つまり、カケイの磯崎への「われわれのために現代美術館をつくって欲しいんだ(*2)」という依頼はほかでもない。われわれ=クルド人のためにクルディスタンの、しかも現代の美術館を設計してほしいという意味だったのだ。だが、時期が時期だけに調査だけで命がけである。そもそも予算はどうするのか。事実、この美術館は実現しなかった。だが、それでも磯崎はこの話に乗ったのだ。 そうだ、急いで補筆しておかなければならない。そもそもがなぜ新潟の砂丘館だったのか。この話の冒頭で触れた洲之内が、『芸術新潮』での「気まぐれ美術館」でカケイについて書いたのは、洲之内の急逝で連載が中断された最後から数えて3番目の回だった(*3)。その洲之内が脳梗塞で倒れたとき、そばにいて洲之内を助けたのが、現在の砂丘館の館長で美術評論家の大倉宏だった。洲之内は終の住処を新潟の山中の小屋と決めており、その夢(?)は実現しなかったけれども、大倉は洲之内の最晩年、なにかと頼りにされた人物でもあったのだ。 カケイの絵にはこのように、多くの死者のこだまが響き合っている。クルディスタンだけではない。洲之内も、針生も、磯崎も、彼の絵のなかで密やかな会話をしている。そしてその響きの集積が、彼の絵の魅力をかたちづくっている。 *1──魯迅と中国版画の革新については以下の記事を参照した。「魯迅、中国で「版画の父」として再評価 上海に展示館」『日本経済新聞』(2021年12月1日) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM017LA0R01C21A1000000/ *2──磯崎新『瓦礫の未来』青土社、2019年、48頁。 *3──洲之内徹「誤植の効用」『さらば気まぐれ美術館』新潮社、1988年。
目次