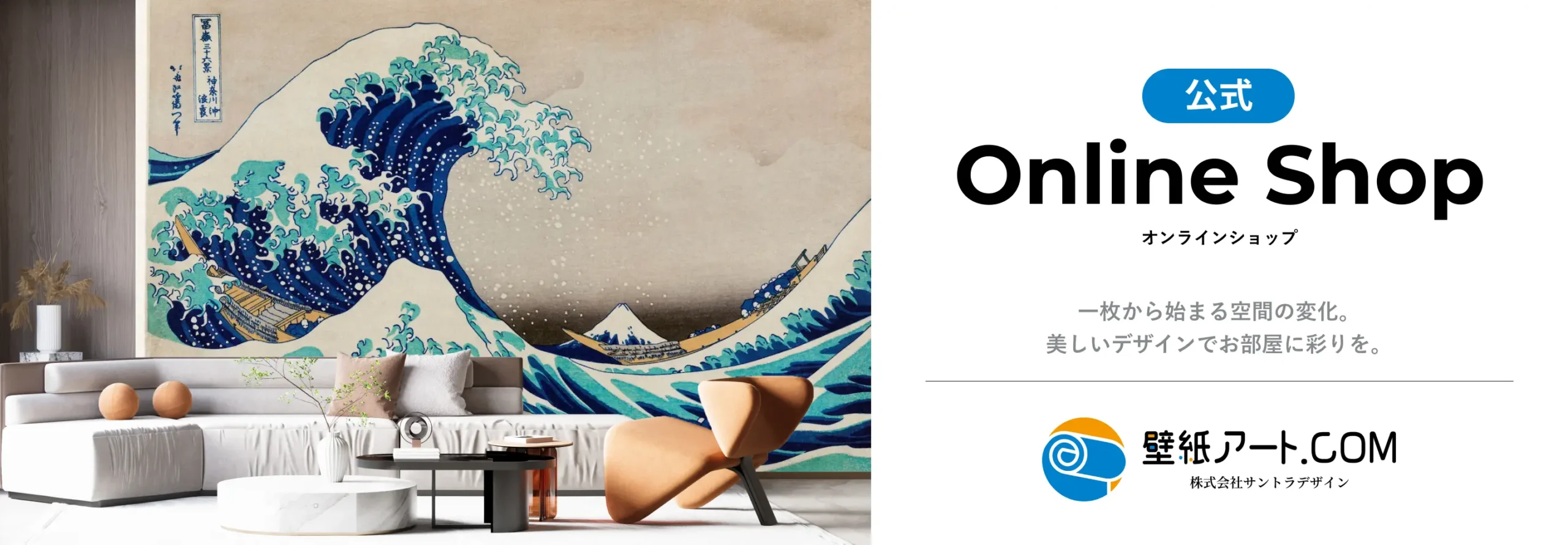明治末から昭和前期にかけて活躍した花鳥画の絵師・小原古邨(おはら こそん)の没後80年を記念する展覧会が、4月3日(木)から、5月25日(日)まで、東京・原宿の太田記念美術館で開催される。
1877(明治10)年に金沢で生まれた小原古邨は、日本画を学んだのち、江戸時代から受け継がれてきた伝統的な浮世絵版画の技法を用いて、淡く繊細な色彩の花鳥画を生み出した。美しい花々とともに、愛らしい鳥や動物たちの姿を温かなまなざしで細やかにとらえた古邨の作品は、欧米で高く評価され、海外にも多くのコレクターがいる。ところが、日本では、1945(昭和20)年に古邨亡きあと、その存在はしばらく忘れられていたという。近年になって注目を浴び、2018年の茅ヶ崎市美術館での展観以来、各所で展覧会が開催されてきた。太田記念美術館で2019年に開催された『小原古邨』展は、1日あたりの入館者数が歴代2位になるほどの人気を集めている。 今回、同館で6年ぶりとなる展覧会は、古邨の画業のうち、明治末から大正にかけて、版元の松木平吉や秋山武右衛門から刊行された古邨の落款が入った作品を中心に紹介するもの。前後期で全点展示替えがあり、計約130点が並ぶ。葉を笠がわりにして踊るキツネや、白い木蓮の木にとまる黒い九官鳥など、いずれの作品も精緻な彫りや摺りの技から生み出される繊細な線と水彩画を思わせる瑞々しい色彩が印象深い。なお、出品作の約4分の1が、前回の『小原古邨』展では展示されなかった初出品作となる。 同展にはまた、歌川広重や葛飾北斎、河鍋暁斎(きょうさい)、渡辺省亭(せいてい)、幸野楳嶺(ばいれい)など、古邨の先駆けとなる江戸・明治の絵師たちによる個性あふれる花鳥画の版画や版本も登場する。つい先頃まで知る人ぞ知る存在だった古邨の魅力とともに、浮世絵における花鳥画の歴史と魅力にも改めてふれることのできる貴重な機会だ。
<開催概要> 『没後80年 小原古邨 ―鳥たちの楽園』 会期:2025年4月3日(木)~5月25日(日) ※会期中展示替えあり 会場:太田記念美術館