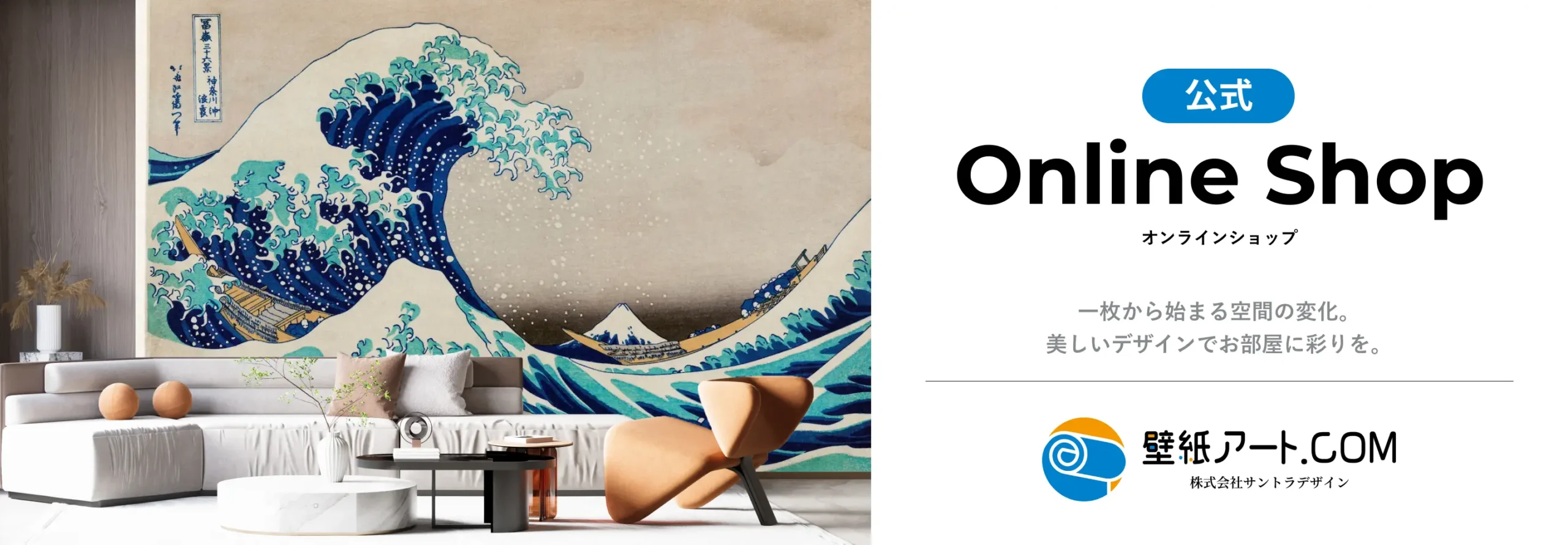| 「生誕150年 池上秀畝―高精細画人―」展 |
|---|
| 会場:練馬区立美術館(東京都練馬区貫井1-36-16) |
| 会期:2024年3月16日(土)~4月21日(日) |
| 休館日:月曜休館 |
| 開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで) |
| アクセス:西武池袋線中村橋駅から徒歩3分 |
| 入館料:一般1000円、高校生・大学生及び65歳以上74歳未満800円、中学生以下及び75歳以上無料ほか。 |
| ※詳細情報はホームページ(https://www.neribun.or.jp/museum.html)で確認を。 ※4月1日(月)に展示替えあり |
「新派」「旧派」というと、まず頭に浮かぶのが「演劇」だが、「日本画」の世界でも「新派」「旧派」の別があったそうだ。演劇の「新派」は明治20年代、明治維新で禄を離れた旧士族が窮状を訴えるために始めた「壮士芝居」が源流で、伝統演劇である「歌舞伎」に対する言葉として定着した。日本画の「新派」は東京美術学校など明治以降に出来た教育制度のもとで様々な技法を学びながら画技を磨くもので、旧来の師弟関係に基づいた「画塾」で学ぶスタイルが「旧派」といわれたという。つまり、演劇も絵画も、江戸時代から続くギルド的な制度のもとで伝統的な技を学ぶのが「旧派」で、その枠を離れて新たな表現の世界を切り開こうというのが「新派」だったわけである。その「旧派」の代表格と目されるのが、今回の“主人公”、池上秀畝(1874~1944)である。


〈近代日本画の研究は、この数十年の間に見直しが進みましたが、菱田春草や横山大観に代表される新派を中心に展開し、秀畝らに代表される旧派については、あまり進んでいないのが現状です〉。展覧会図録の「はじめに」では、こんなことが書かれている。では、その代表と言われる秀畝は、どんな人生を送り、どんな作品を残したのか。秀畝生誕150年にあたる2024年、その画業を改めて検証するのが、この展覧会である。
展覧会は〈プロローグ 池上秀畝と菱田春草 日本画の旧派と新派〉〈「第一章 「国山」から「秀畝」へ〉〈第二章 秀畝の精華―官展出品の代表作を中心に〉〈第三章 秀畝と写生 師・寛畝の教え、“高精細画人”の礎〉〈第四章 秀畝と屏風 画の本分〉〈エピローグ 晩年の秀畝 衰えぬ創作意欲〉の6ブロックに分かれる。まずは「新派」と「旧派」の比較から。秀畝と同い年で「新派」の代表格と言われたのが、菱田春草(1874~1911)。同じ長野県南部の出身だが、西洋画の技法を取り入れて「朦朧体」といわれる独自のスタイルを生み出した。その春草の作品と秀畝の作品を並べてみせる「プロローグ」は、展覧会全体のテーマを内包しているといえるかもしれない。


「新派」と「旧派」の違いをまず見せたところで、展覧会は秀畝の画歴を改めて振り返る。父、祖父ともに絵を良くした秀畝は、幼い頃から自身も絵に親しんでいたという。〈元は高遠藩出入り商人で、裕福な商家だった生家は、祖父の代から家業はもっぱら番頭任せ、趣味にのめり込む当主たちであった〉と展覧会図録で長野県立美術館学芸員の松浦千栄子氏は書いている。上に挙げた《がま仙人》は秀畝9歳の時の作品だというが、画題の渋さといい、禅画風の軽妙なタッチといい、とても子どもの手によるものとは思えない。


15歳の時、荒木寛畝に弟子入りした秀畝だが、当時の寛畝はまだ長屋暮らしの身で、内弟子を取るのは秀畝が初めてだったという。寛畝のもとで、秀畝は「臨模」とともに「写生」を徹底的に学ぶ。修練を積んだ“高精細な”スケッチが並ぶのが、「第三章」である。花鳥だったり、タヌキなどの動物だったり、カエルだったり。修業の成果、官展などに出品した作品を集めたのが「第二章」。個人的に印象に残ったのは、明治44(1911)年の第6回読画会展の出品作品である《日蓮聖人避難之図》。火難から守るため、日蓮を山中へといざなう白猿たちの姿がダイナミック。フォルムがしっかりとしていて、基礎的な画力の高さがうかがえる。


これまでの4ブロックも見どころがあるが、何といっても迫力満点なのは、残りの2ブロックで紹介される屏風絵、杉戸絵など。色鮮やかな草木と戯れる白鷹や孔雀。竹林などの間を飛翔する鷺や鳩。豪華で華麗で躍動的である。〈「鳥」は、花鳥画家として名を成した師・荒木寛畝から受け継ぎ、秀畝が生涯その画力を発揮し続けた題材である〉と展覧会図録にあるが、「なるほど、参りました」と言いたくなる。屏風絵、ふすま絵など、日本画の魅力のひとつは、調度品と一体となった大画面にあると思うが、目黒雅叙園の天井や壁を彩った作品の数々なども見ていると、正確なデッサンを基にした緻密な表現、さらにそれをベースにした自在な構図、そのスケールの大きさに思わず引き込まれてしまう。

さらに図録をひもとけば、秀畝は生前に残した「僕は新派でも旧派でもない」という言葉が目に入る。「新派でも、旧派でもよい作がよいのである」ともいう。「旧派」に分類されている画家ではあるが、考えてみれば師匠の荒木寛畝は一時洋画を手がけた後、日本画に戻ってきた人であるわけで、単に伝統に縛られていたわけではない。伝統を基盤にしながらも独自の世界を切り開いていった、骨太なアーティストの姿が、会場を一覧していくうちに見えてくるのである。「演劇」の「旧派」である「歌舞伎」だって、秀畝が生きた時代には、舞台上でオペレッタをやってみたり気球を飛ばしたり、様々な試みをしているのだ。「旧派」=「守旧派」では必ずしもない。改めてそんなことを思わせてくれた。